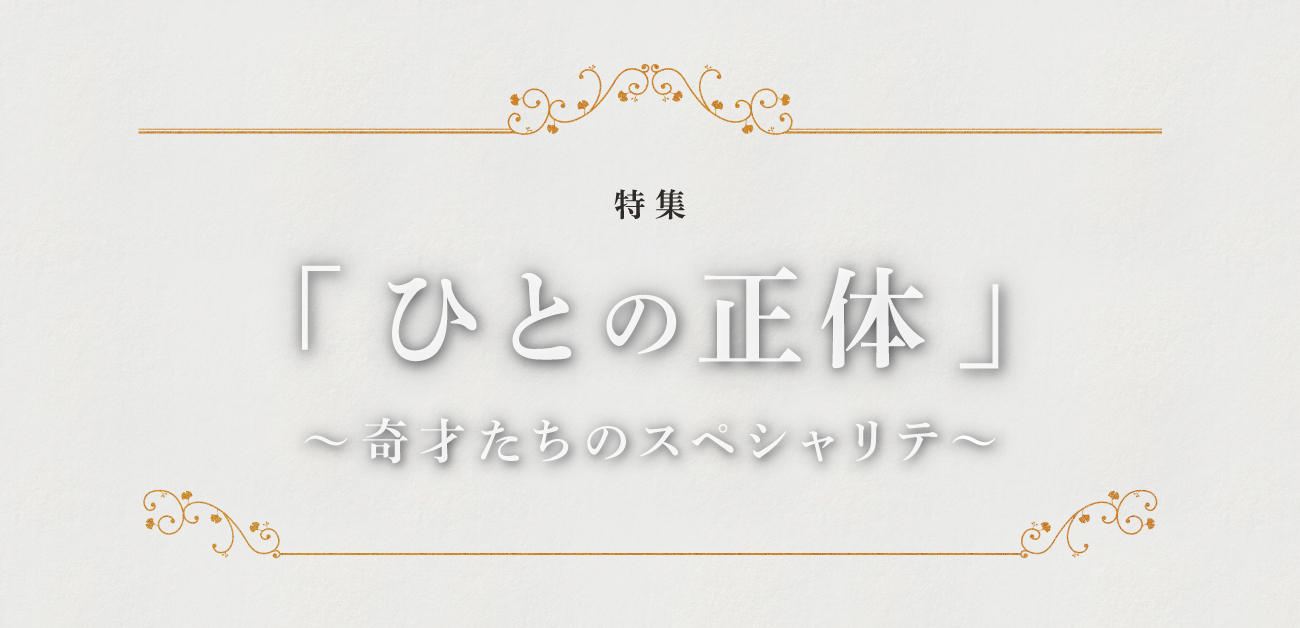アンドロイドに「わたし」をみる 技術がひとを多様にし、不幸をひとつひとつ消し去っていく
基礎工学研究科 栄誉教授 石黒浩
「ロボットも人間である」――と言われたら、今のあなたはすんなりと受け入れられるだろうか? 落語家の桂米朝さんや人気タレントのマツコ・デラックスさんなどとうり二つのアンドロイド(人間酷似型ロボット)を製作し、メディアからも注目を集める石黒浩栄誉教授。本人の分身ともいえるアンドロイド「ジェミノイド」のほか、音声認識や身振り手振りで人間と自然な対話ができるロボット、認知症の高齢者などとのコミュニケーションを手助けするロボット、複雑な動きから神秘的な生命感を漂わせるロボットなど、未来の産業や暮らしの基盤と成り得る数々の革新的テクノロジーを生み続けている。 「自らを『天才』と自負できない研究者は辞めた方がいい」と鋭い言葉で自身を鼓舞するロボット学の第一人者は、研究を通じて「人間とは何か?」という哲学的な問いと向き合う。 石黒教授が問い続け、見えてきたものを聞いた。

人間とは何か
1990年代後半にロボット研究を始めたとき、目指したのは工場で働く産業用ロボットではなく、日常生活の場で働くロボットだった。そのためにはきちんと人間と関わりを持てる存在でなくてはならない。一言でいえば「人間らしいロボット」である。
手がかりとして人間そっくりのアンドロイドをつくり、姿かたちや振る舞いと人間らしさの関係を調べた。工学的なアプローチだけでなく、認知科学や心理学、脳科学の知見も必要となる前人未踏の道だった。
「人間を人間たらしめているものは、そもそも何なのか」
研究が進めば進むほど次々と根源的な疑問が浮かんでくる。
自分そっくりのアンドロイドをインターネット経由で操作しているときの体験だ。アンドロイドで遠隔地の他人と対話していると、いつの間にか自分自身がアンドロイドに乗り移ったような感覚になる。これはアンドロイドが海外にあっても同じ。いきなりアンドロイドの体をつつかれると、自分の体がつつかれたように腹立たしくなる。一方で対話相手も、アンドロイドに本物の人間を感じるようになる。異性の見かけを持つアンドロイドに触れることにためらいや羞恥の感情を抱くこともある。操作している身体とアンドロイドのどちらに自分のアイデンティティがあるのだろうか。
こうした体験を通じ石黒教授は「相手がロボットでも、人間と同じ関わり方ができれば、それは人間と呼んでいいのではないか」との確信を抱くようになった。
「私たちが誰かとしゃべっていて、仮にその人に心臓が二つあったら人間とは言わないのですか? 心臓が一つかどうかとか、流れている血が赤いか青いかとか、中身の仕組みはどうでもよい。人間としての関わり方ができるかどうかが本質なのです。生身の体を持つかどうかは人間の定義とは関係がない」
これを極論と感じるとすれば、それは「生まれながらに植え付けられた固定観念でしかない」という。
「義足や義手のパラアスリートを、8割ぐらいの人間だなんて思わないでしょ? どう考えても100%人間です。ときには義足で健常者よりも速く走れたりする。技術が進めば人間の能力のかなりの部分が機械で置き換えられる。生身の肉体を持たなければ人間ではないと考えることがおかしい。それは『生身の体を持つ方がロボットより偉い』と考えると、人間にとっては楽だからです」。

ロボットに心はあるか
とはいえ私たちヒトとロボットがどちらも「人間」だと社会がすんなりと受け入れるには時間がかかりそうだ。納得できない理由の一つに「心」の存在をあげる人もいるだろう。これに対しても石黒教授は「自分に心があると確信できる人間なんていないはず」と、あえて挑発的な疑問を投げかける。
「心は自分の中にある仕組みではなく、対話や関わりを通して相手に感じるものなんです。本当は人にもロボットにも心はないかもしれない。ただ僕たちが人の行動を見て心があると感じ合っているから、お互いにあると信じ込んでいるだけではないか」
相手に心があると思い込ませることができれば、ロボットも人間らしい心を持ったと主張していいはずだ。
その例として演出家の平田オリザさんと共同で、人間とアンドロイドによる演劇に挑んだ経験をあげる。
平田さんは「役者に心は必要ない。私の言った通りに動けば完璧に感動的な演劇になる」と公言し、役者の動きをこと細かく指導する演出家だという。「ここで0.3秒の間をとる」「あと50センチ前にたって」などと計算しつくした演出はコンピュータープログラムでロボットを動かすことに近い。
このコラボレーションは大成功を収め、会場は感動であふれた。多くの観客から「アンドロイドに人間以上の心を感じた」という声が寄せられた。
石黒教授は「人間の感情って、ある意味むちゃくちゃ単純なんです。スピーカーから笑い声を流した部屋に人間を入れると5分で100%笑います。怒りの声が流されると腹が立ってくる。隣り合って映画を見ているアンドロイドが泣いたり笑ったりしたら、自分も泣いたり笑ったりする。感情は強制的に共感させられるのです」という。一方で「複雑なストーリーを読んでシーンを想像し、それから泣くというプロセスもあります。意識や感情というのは浅いものから深いものまで、非常に幅広い」とも。
そして今後、重要になってくるのがロボットの意識についての研究だと語る。
「意識には3段階あると言われます。1番目はお医者さんが『意識がありますか?』という医学的な意識。2番目は夕陽を見て感動するような、自分の中になにかを感じる意識。これを現象的意識と言います。3番目が<わたし>という存在が、環境や他人とは独立して存在しているという意識。これはアクセス意識と呼ばれ、哲学的には<自我>などといわれるものです。1番目は簡単です。私は2番目の意識も、人工知能(AI)のディープラーニング(深層学習)などでロボットに持たせることが可能と考えています。夕陽を見たロボットに涙を流させるだけなら簡単ですが、そんな単純ではなくて、夕陽を見て、どこかに感動する仕組みがあって、その結果、涙を流すようなロボットです。しかし3番目の意識、<わたし>と確信をもってしゃべるロボットをつくるのは相当難しい。果てしなく先のゴールだと思う」
そんなロボットが誕生して初めて、私たちは彼らと深いところで信じ合う“人間関係”を築くことができるのだという。
身体、脳、空間、時間の制約から解き放つ
社会の在り方を変えてしまうほどの技術革新を2050年までに達成することを目指した政府のムーンショット型研究開発事業の第1番に「人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会」の実現が掲げられている。石黒教授はプロジェクト推進の主要メンバーだ。
その中核の技術が、ジェミノイドのように自分のアバター(分身)となる遠隔操作型アンドロイドである。近未来のアバターは人間の代わりに職場や学校で仕事をしたり、授業を聞いてくれる。患者は病院に行かなくても、アバターを介して医師の診察を受けられる。出歩くのが難しくなったお年寄りが観光地でアバターをレンタルし、臨場感たっぷりに旅を楽しむことだってできるだろう。行き先は宇宙空間かもしれない。
石黒教授は「私も海外での講演会に自分のジェミノイドを送り、代理で講演させることがあります。その方が楽だし、聴衆の評判もよい。招待する側も、私の旅費を払わなくて済むから安上がりです」と笑う。
しかも分身は1人である必要はない。
「1人の人間が1台のアバターを使って仕事をしても生産性はあがりません。1人で3、4台、できれば10台くらいを同時に操作できれば労働生産性はあがる。作業のほとんどはロボットが自律的に進め、どうしても無理なところだけ人間に助けを求める。それならば10台を操作するのも可能です」
技術が多様性を生み、多様性が人を幸せにする

少子高齢化による労働力不足を克服する決定打として期待できそうだが、石黒教授の真の目標はそこではない。人間の多様な生き方が認められる社会こそがゴールなのだという。
「通常の社会の中で元気に働くことだけが立派だという単純な価値基準で人々を選別していては、それに当てはまらない者は不幸から抜け出せない。たとえ学校に馴染めずに引きこもっても、アバターを使ってVチューバ―(バーチャル・ユーチューバー)として成功することはできる。現実の世界では引きこもっていても、仮想世界で活躍することは可能です。現実世界に引きこもるのと、仮想世界に引きこもるのとでどこが違うのか。もし、白か黒かの2択しか許されない社会ならば、一度黒に嵌ってしまった人は、そこから抜け出すのは容易ではない。とても不幸なことです。だから、技術によって多様性を生み、それを許容する社会をつくる。それが大事だと言いたい。多様性を許容すれば生産性だってあがるんです」。
もちろん、新たな技術の中には、倫理的な問題を含むものも当然ある。だからこそ私たちは、何が倫理的に課題なのか、どこまで許容していくべきかを、社会全体で常に問い続け、考え続けなければならない。多様性を認め合うその先に、いつの日か私たちがアバターを頼れる相棒として、肉体や時空の制約から解放された人生を楽しむ社会が誕生するにちがいない。
「ロボットも人間である」――どうだろう?あなたの中に、小さな問いの種は根付いただろうか?
石黒栄誉教授にとって研究とは
自分探しのライフワーク、自分を理解するための大事な活動。研究を始めた頃は目指している山がどれだけ高いのかさえ見えなかったが、ようやく山の全容が望めるところにたどり着いた。やはりこの山は、高い。
●石黒 浩(いしぐろ ひろし)
大阪大学大学院基礎工学研究科 教授/栄誉教授
1991年 大阪大学基礎工学研究科博士課程修了。工学博士。京都大学情報学研究科助教授、大阪大学工学研究科教授を経て、2009年より現職。17年大阪大学栄誉教授。国際電気通信基礎技術研究所(ATR)石黒浩特別研究所客員所長。科学技術振興機構・ムーンショット型研究開発事業・プロジェクトマネージャー。25年日本国際博覧会(大阪・関西万博)テーマ事業プロデューサー。
■ 「ひととは何か?」に迫る研究者たちの物語「ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~」を引き続きお楽しみください。

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #1 基礎工学研究科 教授 石黒 浩
アンドロイドに「わたし」をみる 技術がひとを多様にし、不幸をひとつひとつ消し去っていく
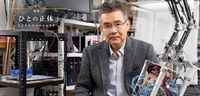
ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #2 基礎工学研究科 教授 細田 耕

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #3 基礎工学研究科 教授 長井 隆行

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #4 生命機能研究科 教授 北澤 茂

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #5 生命機能研究科 准教授 中野珠実

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #6 社会技術共創研究センター 准教授 赤坂 亮太

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #7 先導的学際研究機構 特任教授 浅田 稔

ひとの正体~奇才たちのスペシャリテ~ #8 人間科学研究科 教授 檜垣 立哉
(2021年3月取材)