
ネイティブが説明しづらいことほど面白い! フランス語の前置詞を通して見える「世界」の捉え方
言語文化研究科 言語文化専攻 博士課程3年 梶原 久梨子さん
私たちが日常的に何気なく話している言葉。その一つひとつを丁寧にひも解くと、その言語が根ざす文化や、人々が世界をどのように捉えているのかが浮かび上がってくる。梶原さんが着目したのは、フランス語の「前置詞」。多様な場面や用途で用いられる前置詞を手がかりに、フランス語話者にとっての時間や空間、そして物事の捉え方を探究している。
初めて触れた「言語学」の魅力
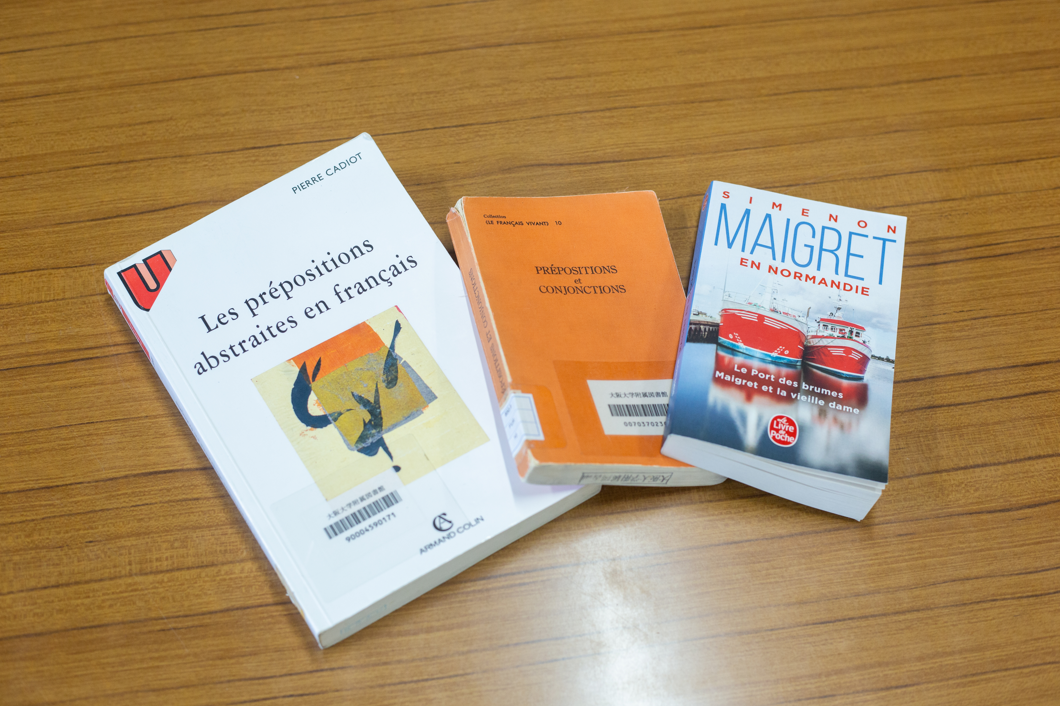
「明日は娘の誕生日だった!―誕生日は未来のことなのに、なぜ過去のことのように話すのか?」学部時代、フランス語学の授業で出会った問いかけが、梶原さんが言語学に興味を持つきっかけとなった。「フランス語でもそのような場合は過去形を用いると知り、日本語とかけ離れた言語でも時間を同じように捉えることがあるのか、と驚いた」。
「難しい文法や単語を覚えるもの」という言語学習へのイメージが大きく変わった。言語には、その言語を話す文化特有の時間や物事の捉え方が反映される。それならば「言語を手がかりに、その言語の話者が世界をどのように捉えているのかを理解できるのではないか」と言語学への好奇心が尽きることはなかった。こうして言語学者を志し、当時在籍していた大学院を中途退学してフランス・パリ大学へ留学。コロナ禍で帰国を余儀なくされるという予想外の出来事もあったが、無事に修士号を取得した。そして、言語学に興味を持つきっかけとなった教授のもとで研究を続けるため、大阪大学の博士課程に進学した。
丁寧に紐解く、「無色透明」な前置詞の意味
フランス語で「無色透明」といわれるほど汎用性の高い前置詞がある。「à」と「de」だ。梶原さんは、それらの意味を取り出すことを目的とし、様々な構文におけるàとdeの機能に関する研究をスタートした。まず注目したのは、「〜を続ける」という意味を持つ動詞「continuer」。英語では「continue」の後に「to」が続くが、フランス語の「continuer」の後には「à」(「〜へ」「〜に」など、英語のtoやatに近い)もしくは「de」(「〜の」「〜から」など、英語のofやfromに近い)が用いられる。興味深いのは、どちらを使っても「〜を続ける」という意味が変わらない点だ。これらの使い分けは一体何に基づくのか。ネイティブも「好みの問題」としか答えられないこの問題に挑んだ。まず、大量の言語データである「コーパス」を用いて「continuer à」と「continuer de」のそれぞれの使用頻度やパターンを分析し、仮説を立てる。そしてフランス語母語話者に文の容認度を尋ねる「インフォーマント調査」を行い、仮説を実証する。複数の手法を取り入れることで研究の質を向上させ、より確実で精緻なものへと仕上げていった。その結果、àは話し手の主観的な評価が含まれるとき、deは話し手が中立的に伝えるときに使われる傾向があることを突き止めた。その後も分析する対象を拡げ、àとdeが含まれる様々な構文のイメージ・スキーマを描くことで、一見するとつながりがないように思える用法の中に共通する意味を抽出した。
ネイティブが論理的に説明できない問題こそ言語学者が研究する意義がある
今回の研究成果について、梶原さんは「世界の捉え方という目に見えない問題に対し、言語学の立場から一つの答えを出せたと思う。ネイティブが論理的に説明することが難しい問いこそ、言語学者が研究する意義があります」と評価する。さらにフランス語を母語としない研究者だからこそ、ネイティブには当たり前すぎて意識しない言語の仕組みを客観的に捉えられるという強みがある。「新しい言語を学ぶことは、新しい世界の捉え方を知ることでもあると思います」。
こうした研究は、梶原さんが非常勤講師としてフランス語の授業を行う際にも活かされている。文法を説明する際に言語形式の背景にあるフランス語話者の考え方や時間の捉え方などを話すと、学生からは「今までの語学の授業とは違う視点でワクワクする」といった声が寄せられるという。春からは、言語学の知見を生かし、「教育開発」の分野でアカデミアの道へ進む。これまでの研究や教育経験をもとに、実際の授業づくりに新たな視点を加えていくつもりだ。

