
音楽が聞こえるとき、脳に「予測」が響いている。前人未到の音楽理論を切りひらく。
人間科学研究科 基礎心理学研究分野 博士課程3年 石田海さん
私たちが日常生活で音を耳にするとき、「音楽」と「環境音」を自然に聞き分けている。この聞こえ方の違いは、どのように生まれているのか。こうした問いに対して、石田さんは先行研究にはない新しい切り口から音楽が聞こえる仕組みを研究している。かつては、声楽を専攻していた石田さん。演奏の道から研究者の道へ転向し、目指す音楽の世界とは。
演奏の道から、研究者へ。一つの疑問からひらいた、探究の扉。
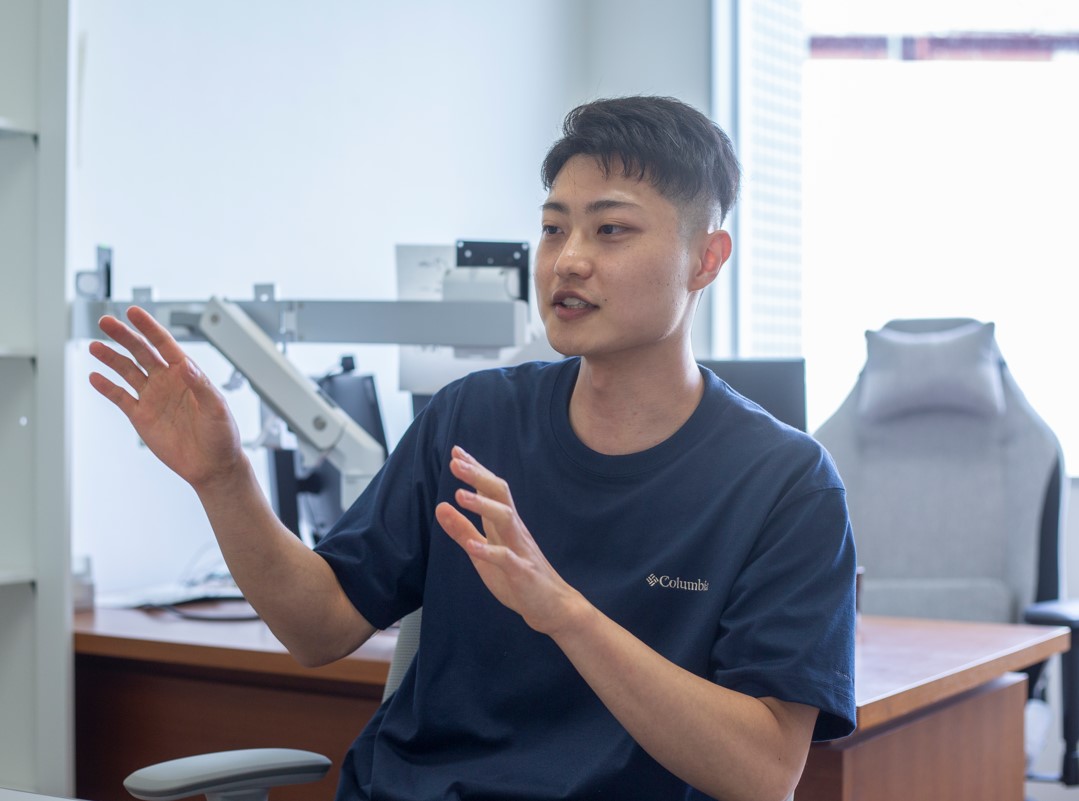
学部時代は、東京にある大学の教育学部で声楽を専攻しながらも、人が音楽を知覚する過程に興味を持ち、心理実験を行ったりしていた。そうした背景から、演奏家としてのキャリアよりも研究者の道に活路を見出した石田さん。国内でも数少ない「音楽×脳」の研究に取り組む大阪大学大学院人間科学研究科の入戸野宏教授にメールを送り、院進学を機に研究室の扉をひらいた。研究のスタートラインは、「音楽が聞こえるってどういうことなのか?」という疑問。例えば、換気扇がまわる「ザー」という音を、音楽として認識する人はあまりいないだろう。しかし、カフェで聞こえてくるBGMは多くの人にとって音楽として聞こえるはずだ。同じ「聞こえる」にしても、両者の違いは何なのか。石田さんの仮説は、「予測」だ。つまり、音を聞いている人が音楽特有の規則性を見出し、次に鳴る音を「予測」できると、音が音楽として聞こえるのではないか、と考えた。
どんな予測が、どんなふうに起こっているのか?
音楽の中での「次に鳴る音の予測」という観点では既に先行研究があり、人は3種類の予測処理を行っているとされる。体系化された音楽理論をもとに次にこの音が鳴るだろうと予測する「スキーマ的予期」。初めて聞く曲でも1番のメロディーを聞いて2番のメロディーを想像できる、というような即座の学習による「動的予期」。既知の曲を聞くと、次に鳴る音を事実として知っていることから生じる「事実的予期」。石田さんの研究では、まずは足がかりとして、音を予測していた時に発生する脳波と、予測から逸脱した時の脳波の分析から、人が音楽を聞く過程での3種類の予測処理で神経反応が現れることを実証した。しかし、これらはあくまで「既にある音楽を、人がどのように予測しながら聞いているのか」という研究であり、「そもそも音が音楽として人に聞こえている理由は『予測』ではないか」という石田さんの根源的な問いとは異なる。先行研究にはない全く新しい発想のため、研究手法そのものから独自に考案・構築し研究に取り組んでいる。実験で使用する音源は自ら作曲。より直接的に問いの答えを出すために、阪大生を対象に、新しい音楽体系で作成した音源を繰り返し聞かせて学習してもらい、既存の音楽にはない「新しい音楽」の予測を作り出そうとする研究を行っている。
「次のステップとして、具体的な予測の内容を読みとるために、機械学習の手法を用いて研究しているところです。将来的には、音が音楽として聞こえ始める過程を解明したり、人がリズムや音楽に『ノる』とはどういうことなのかを予測の観点から調べたり。辿り着きたい成果に対して、現在地は20%くらいですね」。
「予測」がひらく新世界。音楽理論から、配信サービスまで?
「純粋に、自分の学問的な好奇心を満たせることが面白くて楽しいんです」と、早くも研究者の横顔を見せる石田さん。この先も阪大に身を置き研究者としてのキャリアをひらいていきたいと話す。
いつか、まったく新しい「予測」音楽理論の完成に至るかもしれない未開の領域だからこそ、様々な革新の可能性が広がっている石田さんの研究。その応用・発展的なフィールドとして、新しい音楽配信システムの構築にも踏み出したいと期待を抱く。一般的な音楽配信サービスは、AIが人の好みの曲を学習して、同じような好みの人が聞いている別の曲を推薦するというもの。しかし石田さんは、ただ好みの傾向に沿うだけの推薦ではなく、「予測」の観点を活かした相互作用的な提案でその人の好み自体を変化させて、新しい音楽も楽しめるようになるシステムを構想している。
音楽「予測」の研究が、わたしたちの暮らしを取り巻く音楽環境をより豊かに、鮮やかなものにしてくれるかもしれない。

