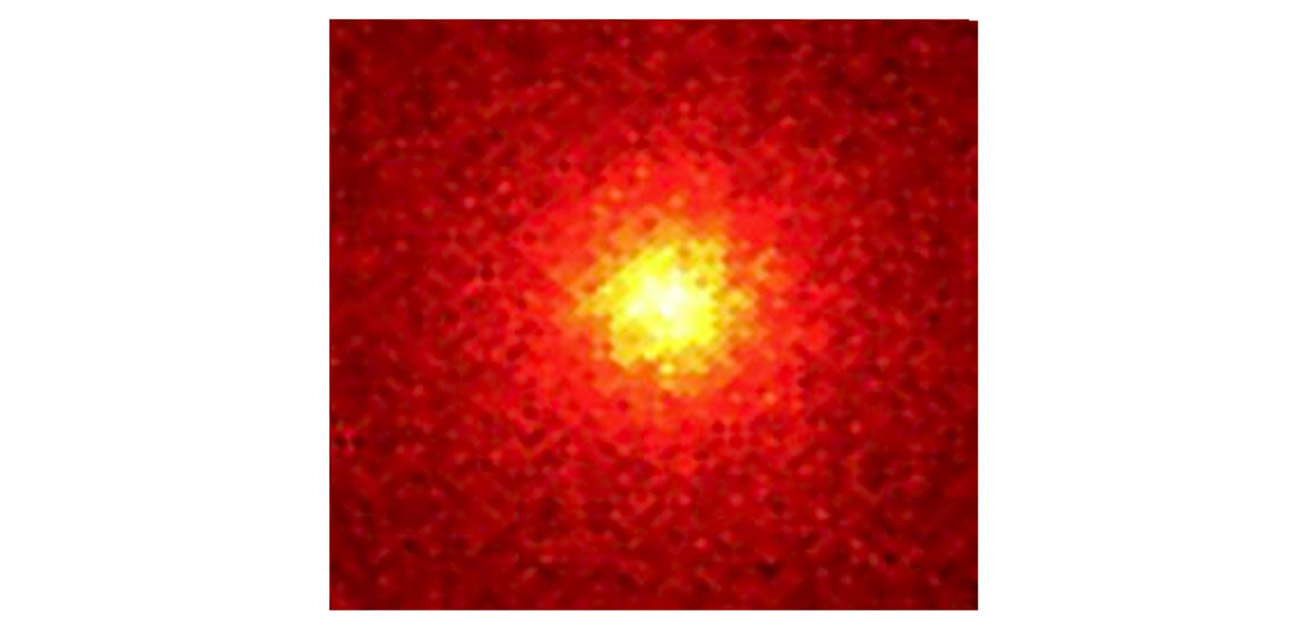
月面観測が「銀河宇宙線」の謎を解く可能性
次世代MeVガンマ線天文学が異分野連携で新展開へ
研究成果のポイント
- いまだ起源が分かっていない銀河宇宙線が月面の物質と衝突して生じるMeV(メガ電子ボルト)ガンマ線を観測することで、これまで探査が極めて困難だった「MeV銀河宇宙線」のスペクトルを間接的に測定する新たな手法を提案。
- MeV銀河宇宙線は太陽磁場や地磁気の影響を受けやすいため、地球周辺で直接観測することができなかった。
- 月面物質と銀河宇宙線の原子核反応で生じるMeVガンマ線スペクトルを理論的に計算し、次世代望遠鏡を用いることで、MeV銀河宇宙線の間接観測が可能になることを示した。
- 銀河宇宙線の起源や加速メカニズムの解明、またMeVガンマ線に特有の核ガンマ線観測によって太陽系や銀河系の環境変動の歴史解明につながる可能性、さらに、月面の放射線環境の理解が進むことで、将来の月面開発や宇宙飛行士の放射線防護設計への応用も期待される。
概要
大阪大学大学院理学研究科の藤原立貴さん(博士後期課程)、井上芳幸准教授らの研究チームは、次世代のMeVガンマ線望遠鏡を用いて月を観測することで、これまで未開拓だったMeV銀河宇宙線スペクトルの測定が期待できることを理論計算により示しました。
銀河宇宙線は、発見から100年以上経過した現在でも起源が明らかにされていません。なかでも、「宇宙に存在するプラズマがどのようにして銀河宇宙線まで加速されるのか」という問いは、宇宙線研究における最大の謎の一つとされています。この問題を解く鍵となるのが、最低エネルギー帯に属するMeV銀河宇宙線の性質を明らかにすることです。しかし、MeV銀河宇宙線は高エネルギー宇宙線に比べて太陽磁場や地磁気の影響を受けやすく、これまで地球周辺で直接観測することができませんでした。
今回、研究チームは、銀河宇宙線が月面物質と原子核反応(衝突)して生じるガンマ線放射現象に着目しました。このようなガンマ線を観測することで、反応の起源になった銀河宇宙線のスペクトルを間接的に知ることができるのです。従来の望遠鏡では、低エネルギー宇宙線の月面核反応に由来するMeVガンマ線を詳細に捉えることはできませんでした。そのため、月を用いたMeV銀河宇宙線の観測に関心は集まっていませんでした。しかし今回、研究チームは銀河宇宙線と月面物質との原子核反応により生じるMeVガンマ線スペクトルを理論的に計算し、次世代の高性能なMeVガンマ線望遠鏡を用いることでその観測が可能であることを示しました。特に本研究では、MeVガンマ線に特有の核ガンマ線を観測することで、MeV銀河宇宙線の百万年スケールにわたる長期変動を調べられる可能性も示しました。この成果により、地球からMeV銀河宇宙線を間接的に観測する新たな方法を提示するとともに、銀河宇宙線の起源解明に向けた一歩となることが期待されます。
本研究成果は、米国科学誌「The Astrophysical Journal」に、7月8日(火)17時(日本時間)に公開されました。
図1. ガンマ線(> 30 MeV)で見た月。黄色に近いほど宇宙線の衝突により明るい。 (Credit: NASA/DOE/Fermi LAT Collaborationより改変)
研究の背景
これまで、MeV銀河宇宙線スペクトルは、地球周辺から観測することができませんでした。なぜなら、MeV銀河宇宙線は、宇宙線のなかで最も低エネルギーの領域に相当し、このような粒子は、太陽系の外から太陽圏へ向かう過程で、太陽風・太陽磁場によって侵入を大きく阻まれるからです。さらに、地球にたどり着いたとしても、地磁気によって遮られるため、地球周辺での観測は極めて困難でした。
一方で、MeV銀河宇宙線スペクトルの直接観測に成功した例もあります。それが、1977年に打ち上げられたボイジャー探査機による観測です。ボイジャーは30年以上の年月をかけて太陽圏の外側まで到達し、太陽磁場の影響がない領域でMeV銀河宇宙線を観測しました。
しかし、ボイジャーが得たMeV銀河宇宙線スペクトルは、星間ガスの電離度から推定されるMeV宇宙線量と一致していません。この現象をより深く理解するためにも、ボイジャーとは別に、MeV銀河宇宙線の新たな観測が求められていました。
研究の内容
本研究では、銀河宇宙線が月面物質と衝突して起こる原子核反応に着目しました。この反応により、磁場の影響を受けないガンマ線が生じます。
図1は、フェルミガンマ線望遠鏡が捉えた、GeV帯(=103 –105 MeV)銀河宇宙線の原子核反応によって輝く月のガンマ線放射の画像です。ガンマ線を生成する具体的なメカニズムは異なりますが、同様の現象はMeV銀河宇宙線によっても発生します。つまり、月のガンマ線スペクトルを調べることで、元となるMeV銀河宇宙線スペクトルがわかるのです。そこで研究グループは、このような月のガンマ線スペクトルを理論的に計算し、将来的に月観測を通してMeV銀河宇宙線の測定ができることを示しました。
図2はその計算結果です(横軸:ガンマ線エネルギー 縦軸:ガンマ線量)。黒線は全ての反応を合算したガンマ線量、その他の線は各ガンマ線生成プロセスの寄与を示しており、青点はフェルミガンマ線望遠鏡によるスペクトルデータを表しています。太陽活動の影響を考慮した宇宙線スペクトルモデルに基づく計算結果(黒線)は、観測データ(青点)全体を非常によく再現しており、モデルの物理的妥当性が確認されました。MeV銀河宇宙線による寄与が重要な0.1—10 MeVのMeVガンマ線領域では、連続スペクトル成分に加えて、異なる同位体元素からの核ガンマ線も明瞭なピークとして複数現れています。従来のMeVガンマ線望遠鏡の性能では月のガンマ線は検出できませんでした。しかし本研究の結果から、2027年以降に始まる次世代MeVガンマ線望計画を用いることで、連続成分と核ガンマ線成分の両方の観測が期待できるとわかりました。なかでも、大阪大学が主導するGRAMS計画は月のMeVガンマ線を捉えるのに有望です。今回の理論計算と比較により、MeV銀河宇宙線スペクトルのより正確な理解が期待されます。
図2. 理論モデルによる月のMeV-GeVガンマ線スペクトル。観測データ(青点)全体を再現。
本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)
本研究成果により、MeV銀河宇宙線の新たな観測手段として、月のMeVガンマ線が利用可能であることが示唆されました。とくに、放射性同位体に由来する核ガンマ線を観測できれば、各同位体の半減期を利用して、MeV銀河宇宙線が過去およそ100万年にわたりどのような変動をしてきたのかを探ることも可能になるかもしれません。これは、太陽系およびその近傍の銀河環境の歴史を理解するうえで貴重な情報となります。一般的な宇宙空間に比べて多様な元素が豊富にある「月ならでは」の特徴を活かした今後の観測に期待が募ります。
また、月面の放射線環境(宇宙線やガンマ線など)を詳しく理解することは、アルテミス計画などに代表される次世代の月探査を安全かつ持続的に推進するための科学的基盤にもなります。本研究は、そのような未来の探査活動を支える科学的知見の一端を担うものです。
特記事項
本研究成果は、2025年7月8日(火)17時(日本時間)に米国科学誌「The Astrophysical Journal」(オンライン)に掲載されました。
タイトル:“The Moon as a Cosmic-Ray Spectrometer: Prospects for MeV Gamma-Ray Observations”
著者名:Tatsuki Fujiwara, Ellis R. Owen, Yoshiyuki Inoue, Manel Errando, Kohei Fukuda, Kazuhiro Nakazawa, Hirokazu Odaka, Keigo Okuma, Kentaro Terada, Naomi Tsuji, Yasunobu Uchiyama, Hiroki Yoneda, and Ao Zhang
DOI:https://doi.org/10.3847/1538-4357/add68b
参考URL
井上 芳幸 准教授 研究者総覧
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/6d8c6508be4b427f.html
SDGsの目標
用語説明
- 銀河宇宙線
銀河内で作られる高エネルギーの粒子放射線。多くは陽子や原子核などの荷電粒子からなる。
- eV
エネルギーの単位。電子ボルト(electron volt)と読む。1 MeV=106 eV
- ガンマ線
約0.1 MeV以上のエネルギーを持つ光(電磁波)の名称。
- スペクトル
粒子や光をエネルギーごとに分解して、各エネルギーの粒子数や頻度の分布をみたもの。
- 核ガンマ線
原子核が放射性崩壊を起こす際に発生するガンマ線のこと。
- プラズマ
正イオンと電子に分かれて自由に運動している状態の物質。物質の三態(固・液・気体)とは異なる状態のため、第四の状態とも称される。
- GRAMS計画
日米が推進するNASA/JAXAの次期MeVガンマ線気球実験計画。大阪大学が主導している。詳細はhttps://grams.sites.northeastern.edu
- 太陽圏
太陽から流出する太陽風の勢力圏のこと。
- ボイジャー探査機
NASAが1977年に打ち上げた探査機の名称。詳細はhttps://science.nasa.gov/mission/voyager/
- フェルミガンマ線望遠鏡
NASAが2008年に打ち上げた衛星。正式名称はフェルミガンマ線宇宙望遠鏡。30 MeV—300 GeVの観測が可能である。詳細はhttps://fermi.gsfc.nasa.gov
- アルテミス計画
米国主導の国際協力体制のもと、アポロ計画以来の月面への有人着陸および長期滞在を通した持続的な月探査を目的としたプログラムの総体のこと。詳細はhttps://www.exploration.jaxa.jp/activities/index.html


