“温度”から探る細胞機能
物理的要因から「生命の不思議」に迫る
蛋白質研究所 原田慶恵 教授
体調が悪い時、とりあえず体温を測ってみる人は多いだろう。言うまでもなく、温度は人間にとってごく身近な物理的要因だ。しかし、生物の基本単位である細胞の機能に対し、温度変化がどんな影響を与えているかは、これまで明らかになっていなかった。原田慶恵教授は、神経細胞内の自発的な温度上昇が細胞分化を促していることを、世界で初めて突きとめた。「熱や温度って本当に根源的。全てに関わっている」。温度という物理的要因を新たな切り口に、細胞機能の解明を目指す研究者に話を聞いた。
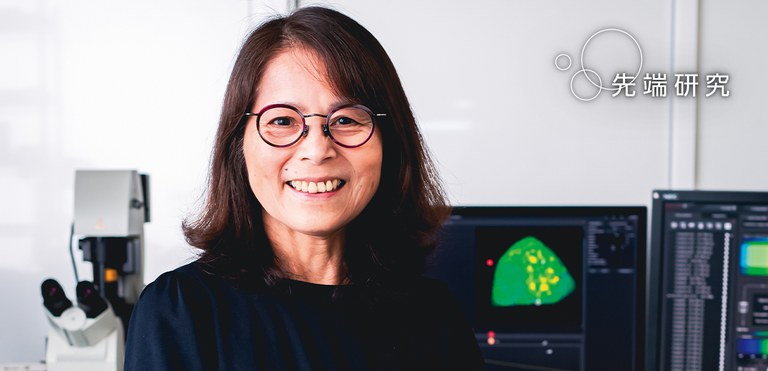
発熱が促す細胞分化
原田教授らの研究グループは今年5月、「細胞内の熱が神経分化を駆動する」と題した論文を発表した。細胞分化とは、未分化の細胞が組織や臓器を構成するために特定の機能や形態を持つプロセスを指す。実験ではラット由来の神経分化モデル細胞を使用した。他の細胞が、タンパク質の発現量や変化まで調べなければ分化したのか分かりにくいのに比べ、神経細胞は「分化すると神経突起が伸びて劇的に形が変わる」ため、一目で分かるのが理由だ。
実験では、赤外線レーザー照射によって細胞の局所的な温度を3℃程度上げたところ、神経成長因子(NGF)の添加による神経突起の伸長が促進された。さらに、NGFを添付しなくても加熱により突起が伸びた。また、細胞内の温度を可視化する蛍光性ポリマー(高分子)温度センサーを用いて分化前後の温度を比較すると、分化した細胞の温度は上昇した。さらに、吸熱性のあるポリマーを使って細胞内の自発的な温度上昇を阻害したところ、神経突起の伸びが著しく抑制され、逆に阻害した細胞を加熱すると突起の伸びが回復した。
これらの結果から、神経分化に細胞内の温度変化が深く関わっていると結論付けた。
神経細胞の機能を熱で制御できるようになれば、「例えば、神経が損傷した人を回復させるのに役立つかもしれない」。神経細胞に限らず、どの細胞も同様の性質を持つと考えており、「普遍的に細胞機能に温度が影響していれば、新たな創薬のターゲットになる可能性もある」と語る。「熱をコントロールする」ことが、再生医療をはじめ、幅広い医工学応用へつながることを期待している。
ナノ量子センサーを開発
細胞内局所の温度を調べる研究が進んできた背景には、温度測定技術の進歩がある。原田教授自身も測定技術の開発に携わってきた。その一つが、ナノ(10億分の1)サイズの人工ダイヤモンド粒子を使った「ナノ量子センサー」だ。髪の毛の太さの千~1万分の1程度の大きさのダイヤモンドが、ある特定の結晶構成を持つと、温度や磁場、電場などの情報を、読み取り可能な光の信号に変換する「量子センサー」の役目を果たす。このダイヤモンドの外側に、緑色の光を当てると発熱するポリドーパミンをコーティングし、ナノサイズの温度計とヒーターが一体化した「ハイブリッドセンサー」を開発した。
「例えば、ミトコンドリアのような細胞小器官にこのセンサーを付着させれば、そこだけを温めることができる。局所の温度変化で細胞機能がどう変わるのか。元気になったり、病気になったりするのなら、それこそ創薬につながる可能性が出てくる」。今後、このセンサーを使って、温度を測るだけでなく、「操作する」実験にも取り組む。
生物“化学”ではなく生物“物理学”から考える
なぜ熱にこだわるのか。
もともと細胞内では、遺伝情報を蓄える核の温度が周りの細胞質より高いなど、温度が一様でないことが分かっている。「ではなぜ不均一性があるのか。細胞の局所で温度が高いところを作ることで、タンパク質の機能の制御などをしているのでは」という仮説が研究のスタートだった。
タンパク質や細胞のメカニズムを調べる際、これまでは重要な機能を持つタンパク質を除去するなどして因果関係を明らかにするような研究が多かった。「分かりやすく、誰もが納得できる。でも、それだけでは説明できないこともいっぱいある」が持論だ。「ゲノム(遺伝情報)が全部解読できても、細胞や命のことは分からないことがたくさんある。それは温度や力、時間など遺伝子に書かれていない物理的要因が重要な役割を果たしているからだと思う」。生物化学だけではたどり着けない真理がある。生物物理学者として、「そこに生命の不思議が潜んでいるんじゃないかなと。それを明らかにできたらいいなと思った」。
もともと生物が好きで茨城大学時代はゾウリムシを研究した。実験好きのあまり「1年365日のうち350日以上は研究室にいた」ほど。「チマチマした実験とかが大好きなんです」と笑う。修士課程修了後は就職するつもりが、実験に夢中になって就職活動に失敗し、縁あって大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程に進学。以来、「生命とは何か、生きるってどういうことなのかを知りたい」と、研究を続けてきた。
来春からは、文部科学省の世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)に採択されている大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(PRIMe)で研究を続ける。病気治療法の開発などを目標に、ヒトのiPS細胞から作ったミニチュア臓器「オルガノイド」などを使って発症のメカニズムを探る研究に参加。ナノ量子センサーの技術を駆使して、細胞機能と物理的要因の関係の解明を目指す。
「これまで周りの方に恵まれて自分の好きなことばかりやらせてもらい、とてもラッキーでした。これから他の分野の方とチームを組んで研究できればいいな」。天真爛漫の言葉がふさわしい笑顔に、根っからの研究者魂がのぞいた。
原田教授にとって研究とは?
研究室が自分の家より好き。実験が大好きで、研究室にいると幸せです。自分の研究に興味を持ってもらい、面白いと思ってもらえるのが一番うれしい。

◆プロフィール
1984年茨城大学大学院理学研究科修士課程修了、88年大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻博士後期課程修了。博士(工学)。日本学術振興会特別研究員や大阪大学基礎工学部教務職員などを経て、慶應義塾大学理工学部専任講師、東京都臨床医学総合研究所副参事研究員、京都大学物質-細胞統合システム拠点教授を歴任。2016年7月から現職。大阪大学量子情報・量子生命研究センター教授、大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点教授を兼任。
■参考URL
(本記事は、2024年9月発行の大阪大学NewsLetter91号に掲載されたものです。
(2024年6月取材)
