雄マウス細胞から卵子を作製
~不妊治療、絶滅危機動物の救済へ一歩~
医学系研究科 教授 林 克彦
雄マウス由来のiPS細胞(人工多能性幹細胞)から作った卵子と別の雄の精子による受精卵から子どもが誕生――。医学系研究科の林克彦教授らのチームが2023年春に発表した研究成果は、世界に大きなインパクトを与えた。その技術は、不妊治療への応用や絶滅危惧種の動物の救済につながるだけでなく、男性同士のカップルが自分たちの子どもを持つ可能性をも示していたからだ。実用化にはまだ時間を要するとはいえ、さらに研究が進めば、社会的な議論を巻き起こす可能性もある。林教授自身は、この研究をどう捉えているのか。
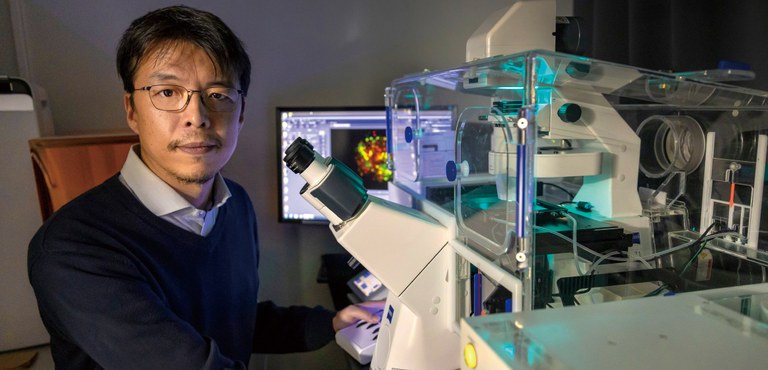
細胞は性別を決めるXとYの染色体があり、雄(男性)はX、Yを各1本、雌(女性)はX2本を持っている。
林教授のチームは、雄の細胞が加齢に伴い分裂を繰り返すうち、Y染色体が消失するケースがあることに着目。雄マウスの皮膚から作ったiPS細胞を繰り返し培養し、X1本だけになった細胞を選び出した。そこに特殊な化合物を加えるなどしてX2本を持つ細胞にし、それを卵子に分化させることに成功した。
この卵子に別の雄マウスの精子を受精させてできた受精卵630個を、雌マウスの子宮に移植したところ、7匹(雄6匹、雌1匹)のマウスが誕生した。いずれも生殖能力を持ち、とくに異常は認められなかった。
「有性生殖のルール書き換える」
英国での遺伝子関連会議で成果を発表したところ、国内外で大きな反響を呼んだ。この技術を人間に応用できれば、理論上、2人の父親が子どもをつくることが可能になるからだ。論文を掲載した英国の科学誌「ネイチャー」は23年末、科学分野で重要な役割を果たした「今年の10人」に日本からただ1人、林教授を選び、「この生物学者は有性生殖のルールを書き換えた」と評した。
林教授自身は「10人」に選ばれたことに「感動や感激より、なぜ僕なのだろうというのが第一印象。そこを目指してやってきた訳ではなく、結果自体はテクノロジーの1つの出口ですから」と冷静に語る。しかし、発表以来、米国を中心に市民団体などからも含めて多くの講演依頼が寄せられており、改めて関心の高さを実感しているという。
「男性カップルが子どもを持つ可能性について頭になかった訳ではありませんが、そもそもの入り口は染色体異常の問題でした」。林教授は、研究をそう振り返る。「生殖には性染色体が重要です。例えば女性のX染色体が1本欠けるターナー症候群は、ほとんどが不妊になります。染色体異常があると卵子ができないことが多く、それを何とかできないかというのが動機でした」。
林教授は京都大学や九州大学在籍時から、マウスの多能性幹細胞を使って精子や卵子を作ることに成功している。これらの技術は「卵子や精子を作るだけでなく、そこに至る過程を体外で再現できる」ことに利点があるという。「人の場合、卵子を作るための重要な過程の大部分は赤ちゃんのときに起きます。それを培養中に体外で見られれば、卵子ができない要因などを知ることができる。基礎研究として何かを知るという点からも重要なツールになります」と説明する。
人への応用は「原理的にはマウスと同じだが、細胞の培養にかかる時間などの条件も違ってくる」ため、まだ10年ほどを要するという。さらに、技術的に可能となったとしても「2人の男性から生まれた子どもが置かれる境遇」などの倫理的、社会的問題も含め、事前に広範な議論が求められると考えている。
「柔軟にテクノロジーの可能性を見せ、広げていくのも私たち基礎研究者の大事な役目です。加えて科学的見地から安全性について示す必要もあります。しかし、技術を使うか使わないかを決めるには、社会的なさまざまな検証が必要だと考えます」。
今後も、人や絶滅危惧種を含む動物への応用を視野に入れながら研究の日々は続く。

キタシロサイ救済にも協力
絶滅危惧種については、林教授は2013年からキタシロサイの救済活動に関わっている。
アフリカ中央部に生息したキタシロサイは、1960年代には2,000頭余が確認されていたが、密猟や内戦、環境破壊などの影響で激減し、世界に母娘の雌2頭しか現存しない。自然繁殖は不可能なため、国際的な研究者チームが絶滅から救うプロジェクトに取り組み、林教授も協力している。
チームは近年、近縁種であるミナミシロサイで体外受精による妊娠に世界で初めて成功した。キタシロサイでも、雌の生体から取り出した卵子に、保存してあった雄の精子を受精させたうえで代理母となるミナミシロサイへの移植を進める予定だ。林教授は22年、キタシロサイのiPS細胞から、精子や卵子のもとになる始原生殖細胞に似た細胞を作ることに成功しており、遺伝子的に多様性を持たせるための技術貢献などが期待されている。
この研究も、実用化に10年はかかるという。「その頃、僕はもう引退(の年齢)です。こういう研究はリレーなので、若い人にどんどん引き継いでもらいたいですね」。
奥深い生命科学
林教授が研究者を志したのは修士課程1年の頃。「受精卵を初めて見て感動したという単純な理由です」。受精卵が発生する様子を見て「細胞はどうやってできるのだろう」と不思議に思ったことが、研究者として探究する「覚悟」を持つきっかけになったという。「それから30年になりますが、研究対象は基本的に変わっていない。進化がないですね」と笑う。
研究の場としての大阪大学については「めちゃくちゃいいところ。分野、人数とも豊富な、さまざまな研究者がいる。しかも、研究者同士の垣根がとても低くて、協力し合う学風がある。その点は他の大学より優れていると思います」と語った。
林教授の研究室には、小・中学校や高校の先生らから「研究の話を聞かせてほしい」という依頼が来ることがある。「啓蒙も僕たちの役目」と考え、若い人に科学への関心を深めてほしいという思いから、時間が許せば受けるようにしているという。
「生命科学はすごく奥が深い。医学、細胞、生物学、進化、環境など多くの学術分野にまたがった基盤となる学問なので、広がりがあり、汎用性も高い。いろいろな分野から入って来てほしい」。そしてこう呼びかける。「私たちもそうでしたが、研究は先人が作ってきた知恵のうえに成り立つ。若い人はそこからもっと先に行けます。歩みを止めず、さらに積み上げてほしい」。

林教授にとって研究とは?
生きる糧であり、趣味であり、友達。研究していると一日があっという間だし、目の前に疑問ややりたいことがあるのがモチベーションになります。 研究の9割以上は苦しくて、思い通りに行くのは1割以下。 僕は「たのくるしい」と言っています。でも、苦労が多いほど、うまく行ったときのうれしさも大きい。 失敗のストレスが、うまくいったことで全部ほどけていく。その瞬間は至福です。
プロフィール
林 克彦(はやし かつひこ)
1996年明治大学農学部博士前期課程修了。
東京理科大学生命科学研究所(分子生物学部門)助手。博士(理学)。05年ケンブリッジ大学ガードン研究所博士研究員。09年京都大学医学研究科講師、12年に同准教授。14年九州大学医学研究院(ヒトゲノム幹細胞分野)教授を経て、21年から現職。
※本件は「大阪大学GUIDE BOOK 2024」に掲載された記事を転載したものです。
(2024年2月取材)
